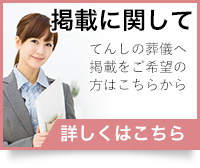遺言書が見つかった時の対処法
遺言が見つかった!さあどうする?
遺言書には故人の様々な想いが込められている大切な文書。遺産分割のときには、もっとも重要な文書として扱われます。遺言書に関連して思わぬトラブルが起こることもありますから、遺言書の扱いについてはしっかりと知っておいた方がよいですよね。
葬儀が終わったら、故人が遺言を残しているかどうか確認しましょう。もし、遺言書を見つけたら勝手に開封してはいけません。遺言書は家庭裁判所で内容を検認(家庭裁判所が遺言書の内容を確認するために調査する手続きのこと)されます。ただし、検認を行わずに遺言書を開封した場合、遺言が無効になるわけではありません。しかし、故意に開けてしまった場合には、最高5万円の過料に処せられることがあるのでご注意ください。
遺言は故人の最終意思と位置づけられ、遺言の内容を最優先する形で財産の相続などが行われます。ですから遺言書を発見したら、適切に保管する方法を考えてください。汚したり、破ったり、ましてや無くしてはいけません。また、遺言書を発見したらすぐに他の相続人にも伝えることもお忘れなく。
遺言書の手続き
遺言書を発見したら、いくつかの手続きが必要になります。まずは検認の手続き。家庭裁判所に持参します。そして約一ヶ月後には同じく家庭裁判所で「開封」の手続きが行われます。開封の手続きは相続人の立ち会いのもと開封しなければなりません。そこで初めて遺言書の内容が明らかになります。
遺言は絶対?
もし、法定相続人が何人かいたときに、遺言書に「財産の全てを○○に譲る」という記載があったらどうなるのでしょうか。原則的には遺言が最優先で扱われますが、法定相続人には遺留分という権利を有していますから、権利を主張することも可能です。そして、相続人の全員の意見が一致すれば、必ずしも遺言通りにする必要はありません。
また、相続人の間で遺産分割協議が行われ、遺産を分けた後に遺言が見つかることもあります。そのとき分割した遺産と遺言の内容が異なっていた場合は、どちらが優先されるのでしょうか?この場合も最大限優先されるのは遺言書となります。しかし、相続人の全員が遺産分割協議を優先させたいと考えている場合、遺産分割をやり直す必要はありません。
遺言がなかった場合
最後に遺言がなかった場合について説明しましょう。遺言がなかった場合は相続人で遺産分割協議を行います。注意したいのが協議は多数決では決まらず、全員の合意が必ず必要になること。協議が不成立となった場合は法定相続の基準に従って分割します。例えば、4人家族で父親がなくなった場合は、配偶者である母親が遺産の2分の1を相続し、2人の子供が残る遺産を分ける形になるため、それぞれ4分の1となります。 分割が確定したら「遺産分割協議書」を作成し、全員で署名と捺印をします。遺産分割協議書は不動産の名義変更などに必要ですから、大切に保管してください。