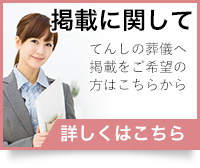訃報を伝える際のマナー
感情を抑え、冷静沈着・的確に対応
いくら心の準備をしているつもりでも、身内の不幸に際しての動揺ははかりしれません。
しかし、今際の際に立ち会えなかった近親者や親族に、一刻も早く事実を伝えるのが訃報の役割です。誰に、いつ、どんな順番で、どの方法で、どんな内容の訃報を伝えるのか。動揺している状態でも冷静沈着・的確に行動できるよう、あらかじめ連絡先のリストを作り、知らせる内容のひながたをメモしておくなどの準備を整えておきたいものです。
訃報を伝える優先順序は、
1 近親者・親族など
2 友人知人・勤務先(商売をしている人の場合は主たる取引先)など
3 ご近所・町内会・自治会など
となっています。
特に近親者・親族への連絡は優先度が高く、早朝・深夜であっても躊躇せず、即座に電話で知らせましょう。訃報を受けた側は「故人が近親者で、遺族から直接訃報を受けた場合は、とにかくできる限り早く遺体のもとに駆けつける」というマナーがあるからです。「先方は高齢者だから、夜が明けてからにしよう」などといった配慮は、後に「他人行儀な。なぜすぐに知らせてくれなかった?」と先方を怒らせる可能性があります。
ただし、健康上の問題などで先方に激しいショックを与えたくない場合は、電話の前に電報を打っておくと、心の準備ができるでしょう。
なお、訃報ではありませんが、葬儀会社への連絡もできる限り早急に行います。葬儀会社は通常24時間電話受付をしていますから、連絡に遠慮はいりません。
友人知人・勤務先への訃報
友人知人・勤務先への訃報は、急いだ方がいいとはいえ、近親者・親族への連絡ほど緊急度が高くありません。故人逝去の事実に加え、通夜・葬儀の日程と葬儀の方法(宗旨宗派や様式など)、喪主の指名と続柄などをあわせて知らせますから、連絡はこれらの事柄が決まってからになります。
もっとも、友人知人の中でも、兄弟同様の親友などは近親者と同列に扱い、こうした事務連絡の前に事実だけを知らせなくてはならないことも少なくありません。また、状況によっては通夜・葬儀の手伝いをお願いしなくてはならない相手もあり、喪主が決まる前に連絡をとらなくてはならない場合もあるでしょう。
また逆に、遠縁・遠方の親戚・親族の場合、本来は真っ先に連絡しなくてはならないところですが、状況に応じて、この段階まで連絡を遅らせても失礼にはあたらないでしょう。
ご近所・町内会・自治会への訃報
ご近所・町内会・自治会への訃報は、友人知人・勤務先への連絡が終わり次第、続けて行います。もっとも、地域によっては、通夜・葬儀に関して近隣や町内と関わりの深い風習がある場合もあります。その地域の慣習によって、連絡の優先順序が変わる場合も考えられます。
友人知人・勤務先への訃報
近親者・親族への訃報は、何よりも事実を早く知らせなくてはなりません。ひとまず「何時何分に亡くなったか」程度を伝え、すぐに駆けつけられる場合は駆けつけてもらい、それが無理な場合は喪主・通夜や葬儀のスケジュールなどの事務連絡を後で行います。
友人知人・勤務先、ご近所・町内会・自治会への訃報では、
・いつ、誰が逝去したのかという事実
・生前の厚情への感謝
・通夜・葬儀・告別式のスケジュール
・葬儀の方法
・香典・供花の類を辞退する場合はその旨
をあわせて連絡します。
死亡報告はがきや訃報メールの場合は、これらに加えて式場までの交通手段や地図などを添えた方が親切かもしれません。